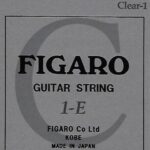クラシックギターという基本的に木でできた楽器の中で唯一機械化が進んでいるのが糸巻です。なぜここだけこんなにメカニカルなのでしょうか?その歴史と構造、そして最近の動向を紹介します。
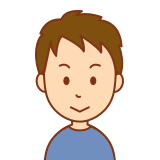
このサイトのクラシックギターの材料や楽器その物に関する記事は以下の記事でまとめてあります:
弦を張り、調整するための糸巻
クラシックギターに限らず、弦楽器のの糸巻の目的は以下の2つかと思います。
- 弦を張り緩まないようにする
- 弦の張りを調整する(チューニング)
弦楽器は弦の張りの強さで音程を調整するものなので、張りが演奏中に代わるのは困ります。また、弦は使っているうちに伸びていくものなので、それに合わせて調整することが求められます。
つまり、緩まないことと精度よくかつスムーズに動かせることが求められるわけです。
摩擦だけで弦を保持するフリクションペグ
最も古典的なタイプの糸巻はフリクションペグと呼ばれるタイプのものです。
フリクションとは摩擦のことを意味し、摩擦の力で弦が緩まないように保持するペグのことを指します。

上はカンボジアの伝統楽器の糸巻です。棒の先に弦を巻き付け、その棒を木に差し込みます。木と棒の摩擦で弦の張力を保持します。弦の張りを調整するときはこの棒を回します。
棒は先に行くほど細くなっており、これをしっかりと木に差し込むことで十分な摩擦を得ます。
ただの摩擦力なので緩みやすい
この摩擦力のみで保持するタイプの糸巻は、当然ながら、摩擦力しかないので非常に緩みやすいという欠点を持っています。
また、手で回した分だけ弦も張られるため、精度を要求される細かいチューニングが難しいです。
リュートや19世紀ギター以前のギターでは主流、木ペグともいわれる
このタイプのペグはギターの祖先といわれるリュートや、19世紀ギター以前の昔のギターでは主流でした。現代のギターの元祖といわれるトーレスもこのタイプを使っていたようです。
これらの楽器では「木ペグ」ともいわれますが、この用語はこの業界だけのもののようです。

ギターの場合はこのように下から上に木の棒を通すことが多いです上の写真は金属棒っぽいので正確には木ペグではないですが)。
今でもレプリカモデルやフラメンコギターの一部では使われていたりします。
今でもヴァイオリンでは主流
このタイプの糸巻は実は今でもヴァイオリン、ヴィオラ、チェロでは主流です。

これは弦によって振動した木の糸巻が木の楽器に振動を伝えていい音を出すともいわれていますが、どちらかというとヴァイオリンという楽器の美意識や伝統的な側面が強いといわれています。
ちなみに、コントラバスはギターと同じく機械式の糸巻を使っています。さすがにあれだけの大きさの楽器になると張力も強すぎてフリクションペグではつらいのでしょう。
ジョン・プレストンが開発した初の機械式糸巻
このフリクションペグの問題は昔から広く知られていました。
そこで、18世紀にジョン・プレストン(John Preston)という人が初の機械式糸巻を開発したそうです(諸説あるそうです)。

この糸巻はPreston Tunerといわれ、シターンと呼ばれる楽器に使われました。上の写真はポルトガルギターのものですが、今でもポルトガルギターではこのタイプの糸巻が使われているそうです。
このタイプの糸巻では金属製の歯車で弦を保持するため、弦が緩みづらくなりました。しかしながら、相変わらず歯車を回した分だけ弦が巻かれるため精度の良いチューニングは難しい機構となっています。
シュタウファーが開発した現代のギターの主流、ウォームギア式の糸巻
この問題を解決したのが18世紀~19世紀のシュタウファー(Johann Georg Stauffer)が解決したウォームギア(worm and gear)式の糸巻です。
これが現代のギターの糸巻の基本的な構造になっています。
回転比を変えてチューニングの精度を上げられるウォームギア

ウォームギアとは上のような構造の歯車のことを指します。クラシックギターのペグを見るとこのような構造になっているのがわかるかと思います。
この歯車のポイントは2つの歯車の回転比です。上の動画だとちょっとわかりづらいですが、よく見と、上の円筒状の歯車が1回転しても下の円盤状の歯車は少ししか回転していないことがわかります。
ギターでは円筒状の方が指で回す歯車、弦が巻き付いているのが円盤状の歯車です。
大きく回しても少ししか動かないので精密チューニング可能
このような構成にすることで、指で糸巻を大きく回しても弦の張りは少ししか変化しません。これによって精密なチューニングが可能となります。
また、大きな張力の弦であっても小さな力で糸巻を回せるようになるのもメリットです。
ちなみに、高級ギターでよく使われる日本の後藤ガット製の糸巻である510シリーズはギア比が1:16になっています。つまり、指でつまみを16回転してようやく弦がローラーに1回巻き付けられます。どうりで弦を張るのに何回もつまみを巻かなくてはいけないわけです(笑)。
さらにちなみに、世界最高峰といわれるロジャースも1:16、アメリカのスローンも1:16、最近人気のアレッシーは1:15、ピンウェルは1:18とメーカーによって様々です。
私は以下の記事のようなアタッチメントを使っています:
シュタウファーの糸巻
シュタウファーはウォームギア式の糸巻を使って19世紀ギターを作りました。これがシュタウファースタイルの糸巻です(この写真はマーティン製のギター):

現代のギターと違い弦を巻き付けるローラーが上方向ですが、これはそれまでのフリクション式の木ペグのスタイルに合わせたのでしょう。一方、ウォームギアをつけるために指で回すつまみは横方向になっています。
こちらは糸巻メーカーのルブナー作っているシュタウファースタイルの糸巻です。シュタウファーが実際に19世紀ギターにつけたのはこのような糸巻といわれています:

歯車がむき出しになっているとそれまでの木ペグに比べて美的に劣っているとおもわれたので美しい彫刻の入ったカバーを付けたのでしょうね。
現代のクラシックギターはむき出しだけどアコギやエレキではカバー付き
クラシックギター用の現代の糸巻はこのウォームギア方式を採用しています。

もはや見た目の要素は気にならなくなったのか歯車がむき出しです。見た目よりも部品交換などのメンテナンス性を重視したのでしょうね。
以外なのがアコギやエレキではカバーがついているのが当たり前という点です。

密閉することで汚れをつきにくくするためのようです。ペグ自体1つ1つ独立しており、壊れたらペグごと交換するというポリシーなのでしょう。
地味に進化しているクラシックギター用の糸巻
クラシックギターの糸巻はこのウォームギアタイプが当たり前であり、構造上の大きな変化はありません。
しかしながら、地味に進化はしています。
金属製ローラー
クラシックギターの糸巻のローラーといえばプラスチックが当たり前でした。

こんな感じの見た目かとおもいます。
このプラスチック製のローラー、使っているとそのうち傷がついたり割れてしまうのが難点です。
このため最近は金属製のローラーが出てきています。

こちらはアルミ製のローラーですが、金属製にすることで耐久性が飛躍的に上がります。
音も少しクリアな音になるといわれていますが。。。
ベアリング付きムービングローラー
さらに最近はローラーの先にベアリングがついているものもあります:

通常のローラーは先端がギターのヘッドの木と触れ合い、回転するときは木と摩擦を起こしながら回転します。このムービングローラーでは先端にベアリングが内蔵されてが動くようになっており、木と触れ合う部分は動きません。これによりさらにスムーズにつまみを回せます。
カーボン製のローラーとプレートを使ったKo-Ga(KG01-CA)
さらに最近ゴトーガットから出たのがカーボン製のローラーとプレートを使った糸巻です。

カーボンですので軽い上に耐久性も高いものと思われます。ヘッドが重いと弾きづらいので、カーボンにして軽くすると弾きやすくなるのでしょうか?
お値段は意外とリーズナブルで、3万円台といったところです。外国製の糸巻が10万円越えが当たり前の中ではリーズナブルです。また、ゴトー製の従来の最上位糸巻であってた510シリーズも30,000円くらいなのでこれとあまり変わりません。
カーボンの見た目なのでギターによって合う合わないがあるかもしれませんが、定評のあるゴトー製の最新ペグなので、ペグとしての性能は優秀かと。
美観を保ちつつ欠点を無くした遊星ギア方式の糸巻
さらに最近になって出てきたのが遊星ギア方式のペグです。

このペグでは惑星が太陽を中心に回るさまに例えてPlanetary Gear(プラネタリーギア)と呼ばれ、日本では遊星歯車とか遊星ギアと呼ばれています。
このギアも上の動画をよく見ると、内側の黒い歯車が一回転しても外側の赤い大きな歯車は半分しか回転していません。この構造でウォームギア方式と同様にギア比を変えています。
外側と内側の歯車が同じ回転軸上にあるのがポイント
この方式のポイントは外側と内側の歯車が同じ回転軸上にある点です。
ウォームギアの場合、2つの歯車は直行していて、つまみとローラーが90度の角度になってしまいました。このためウォームギア方式の糸巻を使うと従来のフリクションペグを使っていた楽器とは違った見た目になってしまいます。
しかしながら、遊星ギアのペグなら回転軸が同じなので同じ見た目のギア内蔵糸巻が作れます。
こちらはオーストラリアのPerfection Pegsという遊星ギア内蔵のペグです:

ぱっと見は普通のフリクションペグなのですが、中に遊星ペグが仕込まれています:

相変わらずヴァイオリン業界では根強い抵抗感がある
この遊星ギア方式のペグ、見た目の問題は解決したのですがまだヴァイオリン業界では根強い抵抗感があるようです。
伝統が長い楽器というのはなかなか新しいものを使うのに時間がかかるので、まだしばらくはフリクションペグが主流なのでしょう。
ヴァイオリン以外ではウクレレにも
ヴァイオリン以外ではウクレレも実はウォームギアを使っていない糸巻が多く使われています。
といっても、木ペグというわけではなく、金属製の棒が突き刺さっているタイプです:

ウォームギア方式を採用しないのは、ウォームギアを使うとどうしても重くて大きくなるので軽くて小さいウクレレと合わないからなのだとか。
そこで、遊星ギアを採用したウクレレ用ペグが登場しています:
クラシックギターで遊星ギアのペグは主流になるのか?
では、この遊星ギア方式のペグは今後クラシックギターにやってくるのでしょうか?
遊星ギアの特徴はコンパクトにできることと回転軸がつまみと変わらないのでフリクションペグと見た目を同じにできることです。
クラシックギターの場合、今のウォームギア方式の見た目が当たり前になっていますし、コンパクトにする必要もなさそうなので個人的には主流になることはないんじゃないかと思います。
19世紀ギターのレプリカなどで実用性を重視した場合に木ペグの代わりに遊星ギア方式のものを採用するのはすでに行われていますので、この路線で細々と使われていく感じではないかと。
クラシックギターの中で唯一の機械製品であり消耗品、メンテナンスを
糸巻はクラシックギターの中で唯一の機械製品です。
そして消耗品であり、使っていくうちに摩耗したり故障したりします。このためしっかりしたメンテナンスを行うことが長持ちさせる秘訣です。メンテナンスについてはこちらの記事を参照ください:
いまいち注目されない糸巻というパーツですが、ギターを演奏するうえでは重要なパーツです。しっかりメンテナンスしていたわってあげましょう。